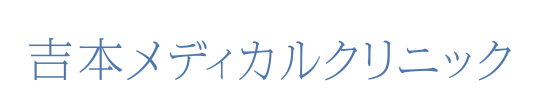新年あけましておめでとうございます。
皆様にとって、今年が希望に満ち、幸福と健康に恵まれた年でありますよう心から願っております。新しい年の幕開けは、新たな始まりを象徴し、私たちにとって未来への新たな希望を抱く大切な瞬間です。
しかし、この機会を借りて、元旦に発生した令和6年能登半島地震の被災者の方々に深い哀悼の意を表したいと思います。この悲劇は私たちにとっても大きな衝撃であり、被害に遭われた方々やそのご家族に心からのお悔やみを申し上げます。また、被災地の一日も早い復興と、全ての方々の安全と安心が確保されることを心から祈っております。
新年の喜びとともに、これらの困難な状況に直面しているすべての人々に、私たちの思いが届くことを願ってやみません。この新年が、再生と再建の年となり、希望と共に前進できることを信じています。
皆様の安全と幸せを祈りつつ、新年のご挨拶とさせていただきます。
敬具