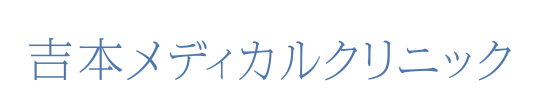人助けは認知症予防に良い?
人助けは認知症予防に良い?
「最近、もの忘れが増えてきた」
「人と関わるのが面倒になってきた」
そんな声を診療の場で聞くことがあります。
脳を刺激する方法として「読書」や「パズル」がよく紹介されますが、
実は最近の研究で、「人を助けること」が脳の健康に深く関係していることが明らかになってきました。
■ 最新研究が示す「助ける行動」と認知機能の関係
2025年に発表された米国の大規模研究では、
30,000人以上の高齢者を20年以上追跡し、
「他人を助ける行動」が脳にどんな影響を与えるかを調べました。
結果は驚くべきものでした。
・人を助ける活動を始めた人は、認知機能が高く保たれやすい
・助ける時間を増やした人は、脳の働きがより安定していた
・特に、「週2〜4時間ほどの人を助ける時間」が、最も効果的でした
つまり、ボランティアや地域の支援だけでなく、
友人を手伝ったり、近所の人を気にかけたりといった身近な行動でも、
脳の健康を守る力があるのです。
■ なぜ「助けること」が脳に良いのか?
本研究は米国のデータによる観察研究(自然な状態のままデータを集めて分析し、新しい知見を得る研究)であり、
因果関係を完全に証明するものではないのですが、
考えられる理由は、いくつかあります。
1. 脳を複合的に使う
人を助けるには、観察力・判断力・共感力など、複数の脳領域を同時に使います。
「人と関わること」自体が、自然な脳トレになるのです。
2. ストレスを軽減する
「誰かの役に立てた」という実感が、自己効力感を高め、前頭葉の活動を活性化します。
3. 社会的孤立を防ぐ
人とのつながりは、抑うつ気分や孤独感を和らげ、生活リズムを整える働きがあります。
■ 今日からできる「脳を助ける助け方」
・ 近所の人に「お元気ですか?」と声をかける
・家族の買い物を手伝う
・困っている友人にメッセージを送る
・地域のイベントや清掃に顔を出す
こうした行動を「毎日ではなく」週に数時間程度続けるだけでも、
脳と心の健康に良い影響があるとされています。
大切なのは、“完璧にやる”ことではなく、
“誰かの役に立つ感覚を取り戻す”ことです。
参考
Helping behaviors and cognitive function in later life: The impact of dynamic role transitions and dose changes(Han et al., 2025, Social Science & Medicine)