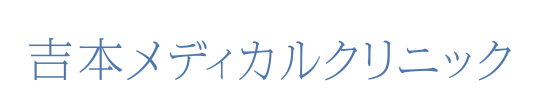成年後見制度のまとめ
ある患者さんを診察中に、家族の資産管理について成年後見制度を使った方がいい場合が思い浮かび簡単に説明したことがありました。
改めて成年後見制度について調べてみました。
○成年後見制度とは
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などの理由で判断能力が十分でない人(被後見人)を法律的に支援する制度です。家庭裁判所によって選任された後見人が、財産管理や契約などの法律行為を代行・補助し、被後見人の権利を守ります。
○成年後見制度の種類
成年後見制度には、大きく分けて 法定後見制度 と 任意後見制度 があります。
1. 法定後見制度
判断能力が低下した後に、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。判断能力の程度に応じて、以下の3つの類型があります。
後見(判断能力がほとんどない場合)
成年後見人が全面的に代理し、財産管理や法律行為を行う。
例: 認知症の高齢者が財産を適切に管理できない場合。保佐(判断能力が著しく不十分な場合)
一定の重要な法律行為(例: 借金、保証契約、不動産の売買など)には保佐人の同意が必要。補助(判断能力が不十分な場合)
本人の同意のもと、特定の法律行為について補助人が支援。
2. 任意後見制度
判断能力が低下する前に、本人が信頼できる人と契約を結び、将来の後見人を決めておく制度。将来的に判断能力が低下した際、家庭裁判所の認可を受けて後見人が正式に支援を開始する。
成年後見人の役割
成年後見人は、被後見人の利益を守るために、以下のような支援を行います。
1. 財産管理
預貯金の管理
不動産の処分や賃貸契約
年金の受領、生活費の管理
2. 身上監護(しんじょうかんご)
成年被後見人の住居の確保及び生活環境の整備、施設等の入退所の契約、治療や入院等の手続など
3. 法律行為の代理・同意
不利益な契約の無効化(取消権の行使)
重要な契約行為の代理(特に後見・保佐の場合)
○成年後見制度の利用手続き
1. 家庭裁判所への申立て(本人・家族・市町村長などが申立可能)
2. 家庭裁判所の審理(医師が作成する成年後見制度用の診断書が必要)
3. 後見人の選任(弁護士・司法書士・親族などが選ばれる)
4. 後見開始(後見人による財産管理・身上監護)
○成年後見制度のメリット・デメリット
・メリット
判断能力の低下した本人を法的に保護できる。
悪質商法などによる被害を防げる。
本人の財産が適切に管理される。
・デメリット
家庭裁判所の監督があるため、自由な財産管理が制限される。
費用(裁判費用・後見人報酬)が発生する。
家族が後見人になれないケースもある。
成年後見制度は、高齢者や障害のある人が適切な支援を受け、安心して生活できるようにする重要な仕組みですが、事前の準備や費用、制度の制約をよく理解して活用することが大切です。
こちらのサイトでより詳細に説明されています。
成年後見はやわかり|厚生労働省