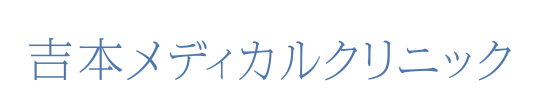「2025年7月5日の大災害予言」が不安…その不安に科学的に向き合う方法
■ なぜ「予言」がここまで不安を引き起こすのか?
SNSやネット上で話題になっている「2025年7月5日に大災害が起こる」という予言。明確な根拠が示されているわけではないにも関わらず、真に受けてしまい不安になる方がおられます。
精神科の外来でも、こうした「予言による不安」を訴えるケースは珍しくありません。とくに過去に災害を経験した人や、もともと不安が強い体質の方は、予言やデマであっても強く反応してしまうことがあります。
では、この不安にどのように向き合えばよいのでしょうか?――ここで有効なのが「認知行動療法(CBT)」という治療的アプローチです。
■ 認知行動療法とは?
認知行動療法(CBT: Cognitive Behavioral Therapy)は、心の不調の背景にある「ものの見方(認知)」と「行動のパターン」に注目し、それらを整理・修正することで、不安や抑うつなどを軽減していく心理療法です。
「2025年7月5日の大災害が本当に起こるのでは?」と不安になるのも、実は思考のクセ(自動思考)や認知の歪みからくるものです。
代表的な認知の歪みに、以下のようなものがあります:
破局的思考:「もし起きたら最悪の事態になるに違いない」
選択的抽出:「過去にも予言が当たったことがあった気がする」
過大評価・過小評価:「政府や専門家は真実を隠しているかもしれない」
未来予測の思い込み:「どうせ何をしても無駄だ、運命だ」
こうした思考パターンを認知行動療法では丁寧に扱い、「事実」と「予測」を分ける訓練をしていきます。
■ 本当に「大災害の予言」は根拠があるのか?
ここで冷静に考えてみましょう。
まず、「2025年7月5日に大災害が起こる」と断言できる科学的根拠は、現時点では一切存在していません。日本政府の地震調査研究推進本部や気象庁、NASAなどの信頼できる機関からも、特定の日付に災害が起こるとする発表はありません。
また、過去の“的中したように見える予言”も、多くは以下のような心理効果の産物です:
バーナム効果:誰にでも当てはまりそうな内容を自分ごととして捉えてしまう
後知恵バイアス:「あの発言はこのことを予言していたのかも」とあとから意味をこじつける
選択的記憶:当たった予言は覚えているが、外れたものは忘れている
つまり「予言」と思っているものの多くは、冷静に分析すれば信憑性のない情報であることがわかります。
■ それでも不安になってしまいます…
不安という感情は、私たちの心が未来のリスクから身を守ろうとする防衛本能です。
大切なのは、その不安を「予言が当たるかどうか」に振り回されるのではなく、自分の内面の課題として捉え直すことです。
「どうして自分は、この情報にこんなにも反応してしまうのか?」
「もともと不安に敏感な性格なのか? それとも最近ストレスが溜まっていたのか?」
こうした“メタ認知(自分の考え方を客観的に見る力)”を育てていくことも、認知行動療法の大事なプロセスです。
■ 今日からできる「不安対処法」
予言に不安を感じている方へ、今日からできる簡単な対処法を紹介します。
① 「証拠」を書き出してみる
「災害が本当に起こるという証拠」と「起こらないという証拠」を紙に書き出し、事実と予測を分けてみましょう。頭の中で考えるだけでは、不安の思考が堂々巡りしてしまいます。
② 情報源をチェックする
その情報は、誰が発信しているものですか? 専門家の意見か、匿名のSNSアカウントか? 信頼できる情報源からの発信であるかを確認することが大切です。
③ 意識的に“今ここ”に戻る
「7月5日に災害が…」という未来の不確実なことに心がとらわれているときこそ、「今日のごはんは何にしよう」「今できる準備はあるか?」など、今この瞬間にできることに意識を戻してみましょう。
④ 必要なら専門家に相談を
もし不安で生活に支障が出ている場合は、無理せずご相談ください。薬物治療や認知行動療法によるサポートが可能です。
■ おわりに:予言ではなく、「今日」を大切に
未来のことは誰にもわかりません。だからこそ「今日をどう過ごすか」に意識を向けることが、心の安定につながります。
災害は“可能性”として備えるものであり、予言に怯えて心身を壊す必要はありません。むしろ、日常の中で不安と上手につき合う力を育てていくことが、私たちを守ってくれます。
吉本メディカルクリニック(東京都港区・心療内科・精神科)では、予言や災害不安に悩む方へのご相談も受け付けています。
不安を一人で抱えず、まずはお話しに来てみませんか?