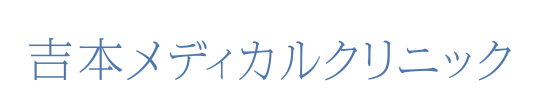これって信じて大丈夫?真実性の錯覚(illusory truth effect)とは?
The Importance of Repetition in the Workplace(職場における繰り返しの重要性)
(The Economist, March 13, 2025)
リーダーに必要なスキルとして、「繰り返し同じことを言い続ける能力」が挙げられ、これは、戦略の浸透、企業文化の強化、投資家やメディアへのメッセージ発信などに欠かせない・・・、
という内容なのですが、記事の途中で、
真実性の錯覚(illusory truth effect)
という言葉が出てきました。
何度も聞くと、たとえ根拠がなくても真実だと感じやすくなる、という意味です。
これについてもう少し調べてみました。
この効果は、1977年に心理学者のHasher, Goldstein,Toppinoによって初めて実証されました。研究では、参加者に一連の文を提示し、一部の文を繰り返し見せたところ、たとえその文が嘘であっても、繰り返し見た文をより「真実らしい」と評価する傾向が見られました。
メカニズムの一つとして、
処理流暢性(Processing Fluency)というのがあり、これは
人間の脳は情報を処理しやすいほど、それを正しいと判断しやすく、
繰り返し見聞きすることで情報の処理がスムーズになり、それが信憑性の証拠のように錯覚されます。
実生活での影響
1. フェイクニュースと誤情報
SNSやニュースサイトで同じ情報が何度も拡散されると、それが事実であるかのように感じやすくなります。デマ情報や陰謀論が広まりやすい原因の一つです。
2. 広告・マーケティング
企業は広告を繰り返し流すことで、商品やブランドの信頼性を高めます。
「〇〇は体に良い」「△△は効果がある」と何度も見聞きすると、実際にそう思い込んでしまいます。
3. 偏見やステレオタイプの形成
ある特定のグループに関する偏見やステレオタイプが繰り返し提示されると、それが事実であるかのように認識されやすくなります。
対策
・情報の出典を確認する。最初に聞いた情報源が信頼できるかチェック。情報源が不明か信頼できなければ信用しない。
・異なる視点の情報を意識的に取り入れる。
・繰り返し見た情報に対して「本当に正しいか?」と意識的に疑う。
・すぐ信用せずに最初から話半分で聞いてみる。
この効果は日常の意思決定や情報処理に大きく影響を与えるため、特に現代の情報過多の社会では注意が必要です。