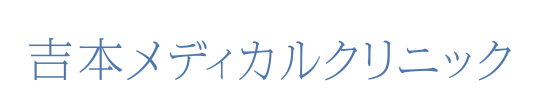「なぜ精神科医は芸能人に病名をつけたがるのか?」
テレビやネットを見ていると、
「この芸能人はADHDっぽいよね」とか「きっと境界性パーソナリティじゃない?」
そんなコメントを目にすることがあります。中には、精神科医を名乗る人がそれらしい診断名を並べて発信していることもあります。
■ 職業病?精神科医は「意味づけ」したくなる
精神科医は、毎日のように「患者さんの言動を見て、診断や処遇を考える」仕事をしています。
いわば、人の行動や感情の背景を常に探っている職業です。
そのため、テレビやネットの中で目立つ言動をする人を見ると、
つい「これは躁状態の一部かも」「自己愛的な傾向が強いのかな」などと考えてしまうことがあります。
これは、ある意味で“職業的なクセ”のようなものかもしれません。
■ 芸能人の言動は「診断ごっこ」の格好の材料?
芸能人はSNSやテレビでの発言・行動が注目される存在です。
一般の人よりも、感情的・衝動的な場面が多く切り取られて流れます。
そうなると、精神科的な目線では「何らかの特性」が浮かび上がって見えることがあります。
・気分の浮き沈みが激しい
・対人関係のトラブルが多い
・感情のコントロールが難しそうに見える
こうした特徴は、精神科医が診療の中でよく目にする症状と重なって見えるため、
“診断名をあてはめたくなる誘惑”が生まれてしまうのです。
■ SNS時代の“疑似症例”のような構造
特にSNSでは、「診断名をつけた投稿」はバズりやすい傾向があります。
フォロワーを集めたい人にとっては、格好のネタになるのです。
また、精神科医の側にも「専門知識をわかりやすく解説したい」「社会に発信したい」という気持ちがあり、
そこに“芸能人ネタ”を使うと、多くの人の関心を集めやすくなるのも事実です。
ただ、診察もしていない相手に診断名をつけるのは、医師として慎重な方がいいのかなと思います。
また、診断名が一人歩きしてしまうと、
「私も同じかもしれない」「こういう人は皆○○なの?」といった誤解を生んでしまいます。
「○○っぽい」と語るよりも、「こういう傾向がある人に対して、社会としてどう向き合うか」を話すほうが、
ずっと建設的で、やさしいアプローチなのではないかと思っています。