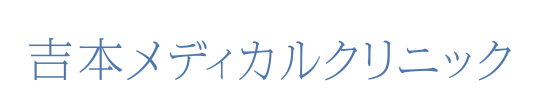吉本メディカルクリニック院長のブログ
-
2025年12月
- 2025年12月14日 二日酔いはなぜ加齢とともに悪化するのか? 2025年12月14日
- 2025年12月11日 自閉症を単一の疾患として扱うべきではない理由〜生物学的理解を深めることで、より良い介入が可能になります 2025年12月11日
-
2025年11月
- 2025年11月28日 【再送】傷病手当金を確実に受け取るためのポイント 2025年11月28日
- 2025年11月14日 🐶🐈ペットヒューマニゼーションとは──「ペットを家族として扱う」時代の心の変化 2025年11月14日
- 2025年11月7日 人助けは認知症予防に良い? 2025年11月7日
-
2025年10月
- 2025年10月25日 ☃️冬のうつに光を ― 自宅でできる「光療法」のすすめ 2025年10月25日
- 2025年10月16日 少女たちのメンタルヘルスにおける静かな危機 2025年10月16日
- 2025年10月2日 今年もインフルエンザ予防接種を開始しました 2025年10月2日
-
2025年9月
- 2025年9月27日 不安なとき「なんとかなる」 2025年9月27日
- 2025年9月7日 悪夢と健康の関係について 2025年9月7日
- 2025年9月6日 タバコ・アルコール・大麻 —— 依存性が一番強いのは? 2025年9月6日
-
2025年8月
- 2025年8月23日 妊婦さんは暑さから守られる必要がある 2025年8月23日
- 2025年8月6日 「よく寝る人ほど健康」は本当? ― 長すぎる睡眠が死亡リスクを高める理由とは 2025年8月6日
-
2025年7月
- 2025年7月25日 日本でオンライン診療が広がらない理由とは? 2025年7月25日
- 2025年7月20日 🗳️今日は参議院選挙の日です 2025年7月20日
- 2025年7月11日 クービビック(ダリドレキサント)とは?―新しいかたちの睡眠薬、その“形”にも意味があります― 2025年7月11日
- 2025年7月6日 「やっぱり何も起きなかった」──2025年7月5日の災害予言と不安の心理 2025年7月6日
- 2025年7月2日 「2025年7月5日の大災害予言」が不安…その不安に科学的に向き合う方法 2025年7月2日
-
2025年6月
- 2025年6月26日 【精神科医が解説】ハローワーク用「就労可能証明書」とは?うつ病・適応障害と仕事復帰の現実 2025年6月26日
- 2025年6月21日 美容整形を受ける人に多い「醜形恐怖症(身体醜形障害)」とは? 2025年6月21日
- 2025年6月13日 【警鐘】鶏チャーシューでギラン・バレー?――カンピロバクター食中毒とメンタルヘルス 2025年6月13日
- 2025年6月7日 【睡眠が脳を守る】デエビゴ(レムボレキサント)が認知症の原因「タウ」を抑える可能性ーでもマウスの場合ね 2025年6月7日
-
2025年5月
- 2025年5月31日 短時間で脳をプチリセット!「パワーナップ」の効果と正しい取り入れ方 2025年5月31日
- 2025年5月29日 心が疲れたときの“栄養ケア”:「トリプトファン」を食事から補う方法 2025年5月29日
- 2025年5月24日 「やりたいことはあるのに動けない」その心理と回復のヒント 2025年5月24日
- 2025年5月17日 人生の主語を「自分」に戻そう 2025年5月17日
- 2025年5月16日 【注意喚起】遺産連絡は詐欺の可能性大|実際の事例と対処法 2025年5月16日
- 2025年5月11日 【会社の悩みは一人で抱え込まない】職場ストレスに上手に対処する方法とは? 2025年5月11日
- 2025年5月9日 曇りの日が続くと「なんとなく元気が出ない」理由 2025年5月9日
- 2025年5月7日 連休明け、気が重いのは「怠け」ではありません 2025年5月7日
-
2025年4月
- 2025年4月26日 良い習慣を作り、悪い習慣を断ち切るには:脳をだます 2025年4月26日
- 2025年4月24日 【重要】傷病手当金を確実に受給するために注意すべきポイント 2025年4月24日
- 2025年4月19日 テクノロジーの活用が高齢期の認知機能低下リスクを軽減するかもしれない 2025年4月19日
- 2025年4月18日 マインドワンダリングとは?――ぼんやりしているときの脳の秘密 2025年4月18日
- 2025年4月16日 【留学中の学生の方々へ】Retroactive Withdrawal(遡及的な履修撤回)とは? 2025年4月16日
- 2025年4月13日 「なぜ精神科医は芸能人に病名をつけたがるのか?」 2025年4月13日
- 2025年4月5日 💬「自分でも思っていないことを言ってしまう…」と悩むあなたへ 2025年4月5日
-
2025年3月
- 2025年3月29日 電子タバコはそれほど有害ではないかも? 2025年3月29日
- 2025年3月27日 眠れないと妊娠しにくくなる?睡眠と女性の妊孕性について 2025年3月27日
- 2025年3月16日 これって信じて大丈夫?真実性の錯覚(illusory truth effect)とは? 2025年3月16日
- 2025年3月7日 マイスリーで認知症になる? 2025年3月7日
-
2025年2月
- 2025年2月16日 断続的な断食は効果がありますか? 2025年2月16日
- 2025年2月8日 成年後見制度のまとめ 2025年2月8日
-
2025年1月
- 2025年1月18日 心と向き合う時間 2025年1月18日
- 2025年1月16日 冬季うつの原因と対策 2025年1月16日
- 2025年1月12日 新年のご挨拶とお知らせ 2025年1月12日
-
2024年12月
- 2024年12月23日 年内の診察は全て終了いたしました。 2024年12月23日
- 2024年12月14日 ストレスを軽減する5つの簡単な方法 2024年12月14日
- 2024年12月13日 うつ病と一時的な落ち込みの違いとは? 2024年12月13日
- 2024年12月12日 年末年始の診療のお知らせ 2024年12月12日
-
2024年10月
- 2024年10月12日 インフルエンザワクチンのご案内 2024年10月12日
- 2024年10月4日 レターパック料金が変わります 2024年10月4日
-
2024年9月
- 2024年9月8日 「不老長寿」は永遠の夢か? 健康に生きる時間をどう延ばす?NHKクローズアップ現代より 2024年9月8日
-
2024年8月
- 2024年8月10日 認知症の発症リスクを減らす方法 2024年8月10日
-
2024年7月
- 2024年7月20日 当院の夏季休暇について 2024年7月20日
- 2024年7月4日 心療内科・精神科において対面診療とオンライン診療の効果に差はありますか? 2024年7月4日
-
2024年6月
- 2024年6月17日 休診日のお知らせ 2024年6月17日
-
2024年4月
- 2024年4月18日 マインクラフトで作ってもらった吉本メディカルクリニック 2024年4月18日
- 2024年4月7日 「残薬があれば遠慮なく医師にお伝えください」 2024年4月7日
- 2024年4月5日 「承知致しました」と「承知いたしました」はどちらが正しいの? 2024年4月5日
-
2024年3月
- 2024年3月10日 睡眠薬デエビゴってどんなお薬? 2024年3月10日
-
2024年2月
- 2024年2月25日 診察における「たわいもない質問」の大切さ 2024年2月25日
-
2024年1月
- 2024年1月5日 新年あけましておめでとうございます。 2024年1月5日
-
2023年10月
- 2023年10月7日 HSP(高感受性パーソン)とは何か? 2023年10月7日
- 2023年10月4日 心のカタチを照らし続けて、10年 2023年10月4日
-
2023年9月
- 2023年9月17日 セロトニン: 「幸せホルモン」の医学的側面とその影響 2023年9月17日
- 2023年9月8日 プラセボ(placebo)効果とノセボ(nocebo)効果について 2023年9月8日
- 2023年9月3日 SNSとメンタルヘルス:ネガティブな影響と対策 2023年9月3日
-
2023年8月
- 2023年8月18日 先生、お薬を飲まない副作用はありますか? 2023年8月18日
- 2023年8月1日 PMSとPMDD:それぞれの特性と違いを理解する 2023年8月1日
-
2023年7月
- 2023年7月16日 "身体症状症と病気不安症:似ているようで違う二つの病態" 2023年7月16日
- 2023年7月13日 身体症状症と精神の健康:一見無関係な二つが密接なつながりを持つこと」 2023年7月13日
- 2023年7月7日 病気を心配する病気ってあるの?病気不安症とは? 2023年7月7日
- 2023年7月4日 当院でのマスク着用は任意です 2023年7月4日
-
2023年6月
- 2023年6月29日 デジタル時代の心の健康:心療内科のオンライン診療 2023年6月29日
-
2022年12月
- 2022年12月16日 傷病手当金がもらえない?気をつけるふたつのポイント 2022年12月16日
-
2020年3月
- 2020年3月6日 新型コロナウイルスについて〜テレビは消しましょう〜 2020年3月6日
-
2018年3月
- 2018年3月31日 診療時間変更のお知らせ 2018年3月31日
-
2017年7月
- 2017年7月12日 ノドが渇かなくても水分を!熱中症について 2017年7月12日
-
2017年6月
- 2017年6月10日 三者面談って誰とするの? 2017年6月10日
- 2017年6月4日 うつ病になったら治療はどうなるの?ーうつ病の治療と経過について 2017年6月4日
-
2017年5月
- 2017年5月29日 寝酒はダメ!アルコールについて 2017年5月29日
-
2017年3月
- 2017年3月19日 タバコについて 2017年3月19日
-
2017年2月
- 2017年2月25日 アスクル倉庫火災と災害医療 2017年2月25日
-
2017年1月
- 2017年1月27日 ジェネリックについて 2017年1月27日
- 2017年1月10日 ウェブのデザインを変更しました 2017年1月10日
-
2016年12月
- 2016年12月19日 仕事から逃げ出す勇気 2016年12月19日
- 2016年12月1日 日本の職場は適応障害の温床である 2016年12月1日